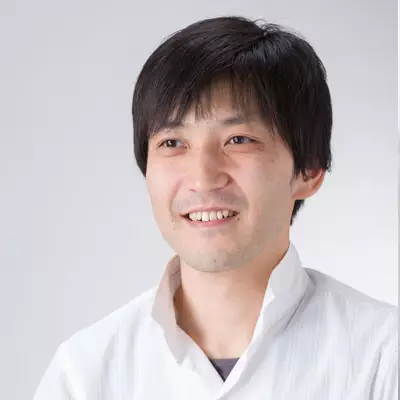エアコンのいらない家
このサイトは株式会社クレアホームをスポンサーとして、
Zenken株式会社が運営しています。
ご家族のリクエスト
- 生活感が出ないようにしたい
- 色合いに統一感を出したい
床に幅の広いフローリングを選ぶほか、電気のスイッチなど小さなところにもこだわりが随所に施されています。
デザイン性に興味があり、建築家の方と工務店が一緒になってやっているという点が決め手となりました。
建築家のアプローチ
この家の建築家
新堀 和巳 / Kazumi Niibori
毎日の暮らしの間(場)を構成する様々な素材の質感に、一手間入れた美しさにこだわって設計しています。
その美しさは、各地の風土、生活の所作、経済性、そして合理的に生まれてくる「健全な美」としてあらわれます。
工業化した素材と、人の技術のぬくもりを合わせながら、その「健全な美」をさらに磨いていきます。
| 所属 |
有限会社新堀和巳建築設計室 |
| 経歴 |
1963年 埼玉県深谷市生まれ
1987年 ICSカレッジオブアート 卒業
1987年 株式会社渡辺明設計事務所 入所
1994年 同チーフデザイナー就任
1999年 デザインヴォイス 設立
2004年 有限会社新堀和巳建築設計室に改名 |
建築家「新堀 和巳」について詳しく見る
住宅における固定概念を揺るがすプラン
南に窓をつけなくても、十分な採光性を確保することができる作りで、「南に窓を作らなければならない」といった住宅における「こうあるべき」に揺らぎを与える作りとなっています。
デザイン性の優れた防音室
吊り天井の中に吸音材を入れることで、照明も吸音も両立したデザインとなっています。
クレアホームより
この事例について「クレアホームだから実現できた」という事柄があれば教えてください。
何気なくTVを置いているカウンターの背面には、腰壁のように見える部分がありますが、実は背面から使える収納になっています。
TVの配線やコンセントを見せない工夫や、カウンターの先端が下がらないように強度を確保するために、細部までこだわって作りました。
完成すると一見シンプルに見えますが、見えないところにも配慮しています。
「クーラーを使わない」というアイディアが出てきたのはどの段階だったのでしょうか?
設計の初期段階で、お客様よりアレルギーもあり、エアコンの風も嫌いとのお話があり、新
堀先生よりご提案がありました。
その後すぐに体感に行き、お客様が心地よさに感動し、採用となりました。
この事例における「規格化していない強み」はどこでしょうか?
パネルシェードの冷温熱が効率よく循環するように、風呂・トイレ・防音室以外は間仕切壁
のないひとつながりの空間となるように考えて作っています。
そのため子供部屋は造作の収納家具でスペースを分け、上部はオープンに。
見た目で収納とわからないよう、家具と扉を同じ面材で造作して一体感のある仕上がりにしました。
お施主様の理想を叶えるために、建築家の設計力と工務店の施工力で要望に柔軟に応えられるのは規格化されていない体制でこそではないでしょうか。
この施工事例や施主様に対するクレアホーム様の想いをお教えください
お施主様自身お家の仕様から、家具や家電に至るまで一つ一つ丁寧に選ばれていて、家と
ともに暮らしを楽しんでおられるのが伝わってくるお家になっています。
良い音楽を奏でてください、仲の良い奥様とともに・・・
「エアコンのいらない家」の味方 パネルシェード
引用元:クレアホーム公式サイト
https://creahome.jp/blog/%E5%A4%89%E3%82%8F%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%86%B7%E6%9A%96%E6%88%BF%E8%A8%AD%E5%82%99%E3%81%AE%E3%81%94%E7%B4%B9%E4%BB%8B/
ここでは、このページで紹介した「エアコンのいらない」の事例で使われている空調設備である「パネルシェード」について深掘りして紹介します。
基本構造
窓枠に設置されたレールに沿って、しっかりとした素材のパネルが上下にスライド。使用時は下に展開、不要時は上部にコンパクトに収納できます。
パネルの特性
断熱材を内蔵したパネルや特殊な反射コーティングを施したものを使用。夏の日差しを効果的に遮り、冬は室内の暖気を逃がさない構造です。
操作方式
手動式から電動式、リモコン対応まで多様な操作方法を選択可能。大きな窓でも楽に開閉でき、生活スタイルに合わせて選べます。
断
高い断熱性と遮光性
従来のカーテンやブラインドとは異なり、しっかりとした素材のパネルで高い断熱性と遮光性を実現
調
年間を通じた室温調整
夏は涼しく冬は暖かい、季節を問わず快適な室内環境を自然の力で実現
光
自然光の有効活用
日射を遮りながら必要に応じて自然光を取り入れ、昼間の照明使用も抑制
パネルシェードの特徴
太陽熱を窓の外側で遮断することで、室温上昇を根本から防ぐ仕組み。
自然の力を活用した、人にも環境にもやさしいシステムです。
1
省エネルギー性
電力をほとんど使わず動作し、月々の電気代を大幅に削減できます
2
快適な室内環境
人工的な風や急激な温度変化がなく、身体への負担が少ない自然な環境
3
静音性
運転音がないため、静かで落ち着いた住環境を保てます
4
メンテナンスフリー
フィルター掃除や定期点検が不要で、故障リスクも低く長期間安定使用
5
健康的な空間
乾燥や体調不良の心配がなく、自然な湿度を保った健康的な室内
6
長期的な経済性
一度設置すれば追加コストがほとんどかからず、長期的に経済的
「パネルシェード」についてのよくある疑問
外付けタイプの魅力
窓の外側で日射を約80%カットし、室内の温度上昇を効果的に抑える遮熱効果が大きな魅力です。実測では直射部の温度が数℃低下した事例もあり、「エアコンの要らない家」の実現に貢献します。
角度調整により、通風と視線カットを両立できます。眺望を確保しながら快適な室内環境を作り出せる点も重要な利点です。
内装側タイプの魅力
ハニカムシェードは、蜂の巣状の空気層により窓辺の断熱性・遮熱性を高めます。
設置が手軽で、インテリア性も高く、細かな調光制御により快適な光環境を実現できます。プライバシー保護と省エネを両立させながら、室内の雰囲気を損なわない点が支持されています。
特に推奨される方
西日の影響が大きい住まい、大開口の窓がある住宅、在宅ワークで眩しさや画面の映り込みを抑えたい方に適しています。
コードレスの電動タイプは操作が容易で、ひも絡まり事故のリスク低減にもつながるため、子育て世帯や高齢者にも扱いやすい選択肢となります。
省エネ志向の方や、高気密高断熱住宅でさらなる快適性・省エネを目指す方にも有効です。ただし、効果は窓の方位・ガラス仕様・運用方法に左右されます。
環境別の適性
都市部の密集住宅地では、外付けタイプにより遮熱と視線コントロールを両立でき、プライバシー確保にも役立ちます。
パッシブハウスやZEH志向の設計では「外部での日射遮蔽」を積極的に採用する事例が多く見られます。ただし必須というわけではなく、地域・方位・意匠計画との総合的な判断が必要です。
マンションの場合、バルコニー等は共用部分の専用使用となることが多く、管理規約で外観変更・外付け機器の設置が制限される場合があります。事前の承認確認が必要です。
戸建ては設計自由度が比較的高いものの、景観・防火等の地域ルールや納まり条件の確認が前提となります。
外付けタイプ
窓の外側に設置する外付けシェードは、室内側の結露を直接増やす要因にはなりにくい製品です。
結露の発生は主に「室内の湿度」と「ガラス表面温度」により決まります。日射遮蔽は温度差の緩和に寄与する可能性がありますが、最終的な発生有無は湿度管理や換気などの運用に依存します。
強風・台風時は、取扱説明書に従った収納などの運用が推奨されます。
内装側タイプ
ハニカムシェードは断熱性が高い反面、閉め切るとガラス面が冷えやすくなり、冬季に室内側で結露が増える傾向が試験で確認されています。
対策として、シェード上下に約1〜5cmの隙間を設けて通気を確保することが有効です(上下併用がより効果的)。あわせて換気・除湿など室内湿度の管理を行うことで、結露の低減が期待できます。
電動タイプの電気代
1台あたりの月額電気代は、主に"待機(スタンバイ)電力"により決まります。
有線タイプの場合、待機電力は1.0〜1.9W/台程度で、31円/kWhで試算すると月額約22〜42円となります。
動作時の定格電力は機種により数十〜100W超となりますが、上げ下げは十数〜数十秒と短時間のため、1回の動作コストは概ね0.01〜0.05円/回にとどまります。
1日3〜5回の操作でも、合計は1台あたり月20〜60円前後が目安となります(実際は機種・台数・運用により変動)。
バッテリー式は年1回程度の充電(最大約6時間)が一般的で、充電に要する電力量は小さく、年間の充電電気代は数円〜数十円程度が目安です(充電器の定格により変動)。
外付けタイプの耐用年数
一般的な目安は10年前後〜十数年です(製品品質・設置環境・メンテナンスにより幅があります)。
紫外線や風雨が主な劣化要因となりますが、耐候性の高い生地・糸・アルミ部材の採用や、適切な清掃・取扱いにより寿命を延ばすことができます。
30年超の使用は例外的で、途中の部品交換・修理を前提とした場合です。
内装側タイプの耐用年数
ファブリック系(ハニカム/プリーツ/ロール等)は概ね5〜10年が目安となります(品質・日射量・操作頻度により変動)。
アルミ/樹脂(PVC等)のブラインドは、素材や使用環境により幅がありますが、概ね5〜10年程度です。アルミ製は丁寧な取扱いにより7〜10年程度の使用が期待できます。
適切な清掃と湿度・日射管理により、寿命の延長が期待できます。
部品交換による機能維持も可能です。国内の事例では、昇降コード交換が1台あたり概ね2,200〜5,500円程度の料金帯となっています。生地の交換・本体更新は、サイズやブランドにより数万円規模となります。